小ジョッキは約300mLでちょうど良い。お店にあると嬉しいサイズ。

札幌駅前の空は、夏の夕暮れにうっすらとオレンジ色を残しながら、徐々に夜の顔へと移ろっていた。
鈴村美晴は商談を終え、大きく息をついて肩の力を抜いた。隣を歩く桃田天音も同じように「ふぅ」と息を吐きながら伸びをする。
「なんとか終わったね。やりきったって感じ」
「ほんと、それ。正直、ここまで準備してきて正解だったわ」
二人は顔を見合わせ、自然と笑みがこぼれる。数週間にわたる資料づくりや打ち合わせの緊張感から解放され、互いにねぎらい合うように笑うのだった。
札幌駅前の街は、観光客や仕事帰りの人々で賑わい、どこか浮き立つような空気が漂っている。
「せっかくだし、今夜は北海道の美味しいもの食べて明日帰ろうよ」
天音が声を弾ませると、美晴も迷わず頷いた。
「やっぱり寿司でしょ。札幌といえば」
そんな会話を交わしながら、二人は札幌駅ビルの6階にある、で評判の回転寿司店へと足を運ぶ。入口には行列ができていた。
待ち人数はなんと75組。案内されるまで2時間はかかりそうである。それさえもこの土地ならではの期待感を高めるスパイスのようだった。
ようやく店内へ案内され、席に着いた二人はすぐにメニューを開いた。そのページの一角に、美晴の目がとまる。
「サッポロクラシック」――。
北海道限定のビールである。関東でもごく一部でしか販売されておらず、常時楽しめるのは北海道民の特権のようなもの。
麦芽の味わいがしっかりとしていて、飲み込んだあとに口いっぱいに広がるホップの苦みは、飲む人を虜にする。
「これだよ、これ。せっかく来たんだし、クラシックいこ!」
天音が迷わず指差すと、美晴も「うん」と頷いた。出張の疲れを癒すにふさわしい一杯になる予感がした。
暖簾をくぐった瞬間、漂ってくる酢飯と海鮮の香りに二人の胸が高鳴った。カウンターの向こうで板前がリズミカルに握る音が響き、レーンを流れる寿司が次々と客の前に収まっていく。

グラスが置かれ、二人の手に渡るまでの時間が待ち遠しかった。
「お疲れさま!」
カチン、と音を立ててグラスが重なる。その瞬間、黄金色の液体がきらめき、泡立ちがふたりの心まで弾ませた。
美晴は一口飲んで、思わず小さく声を漏らした。
「…おいしい。出張先で飲むビールって、なんでこんなに沁みるんだろうね」
「それはさ、頑張ったご褒美だからでしょ」
天音は笑いながら、次々と寿司皿を手に取っていく。

その夜の二人にとって、寿司の味もビールの冷たさも、ただの食事以上の意味を持っていた。数日前まで東京のオフィスで、顔を突き合わせて議論していた自分たちが、今は北の街で笑い合っている。その距離感と非日常が、二人の心を軽やかにしていた。
回転寿司での小さな幸せ

カウンター席に腰を下ろすと、目の前のレーンには北海道ならではの新鮮な寿司が彩りよく流れていた。ホタテの透き通る白、イクラの鮮やかな橙、脂ののったサーモン。どれも目を奪う輝きを放っている。
桃田天音は、まるで宝石箱を覗き込むような瞳で皿を見つめた。
天音の実家は自由が丘にあり、とても裕福な家庭だった。父は業界人で、母も洗練された美貌の持ち主である。
その容姿は天音に受け継がれ、オフィスでもひときわ目を引く存在になっている。だが天音の母は、もともと東北のさらに北の地方の出身で、母子家庭の貧しい暮らしを経験していた。
天音の祖母はいつも地元で安くて良い食材を工夫し、手料理を食卓に並べていた。
結婚して自由が丘での暮らしになってからも、母は幼少時代の教えから外食を避け、家族に自らの料理を食べさせ続けた。娘の天音もその味で育ち、自然と舌が鍛えられていったのだ。
だからこそ、天音の「神の舌」はその生活の中で育まれた。

そんな背景を持つ天音が、最初に選んだのはウニだった。
「ほら、美晴。これ…絶対いっとかなきゃでしょ」
皿を取ってゆっくりと口に運ぶ。ひと噛みした瞬間、天音の表情がふわっとほどけ、思わず瞳を閉じる。
黄金色の粒が舌に触れると、濃厚な甘みがとろりと広がり、海の香りが鼻へ抜ける。クリーミーで上品、それでいて力強い旨味が、口の中を永遠に支配する。
「…これは、本物だわ」
頬を緩ませながらも、言葉には鋭い確信があった。美晴は思わず吹き出す。
「天音って本当に、美味しそうに食べるね」
一方、美晴が真っ先に手を伸ばしたのは、越前ガニを思わせるズワイガニの軍艦だった。
「敦賀じゃね、冬になるとカニが食卓の主役になるの」
そう言いつつ、美晴は懐かしそうに微笑んだ。

鈴村美晴の実家は決して裕福ではなく、年に一度あるかないかの贅沢が、スーパーの特売で買った痩せ細ったカニだった。
小学生だったあの日、身をほじくるのに苦労しながらも、家族みんなで笑顔で箸を伸ばし合った。小さな身でも一口一口がご馳走で、あの光景は今も胸に焼き付いている。
だからこそ、目の前の寿司に盛られた大ぶりのカニの身を食べた瞬間、美晴は思わず目を閉じた。
「…やっぱり、カニには目がないなぁ」
その表情は、幼い日の食卓を思い出しているかのように柔らかだった。天音は横で「子どもみたい」と笑った。
やがて二人の前には空いた皿が積み上がっていく。ホッキ貝の弾む歯ごたえ、サーモンの濃厚な脂、締めサバの深い旨味。どれを口にしても「うわ、美味しい」「これはやばい」と声を上げ、東京ではなかなか味わえない鮮度に感嘆するのだった。

そこにビールを一気に流し込む。二人は思わず唸った。
ごくごくと喉を通る冷たい液体は、一日の疲れを一気に洗い流す。美晴は頬を赤らめながら夢見心地で笑った。
「ほんとに出張ってご褒美だね」
「でしょ?こんな寿司とビールで締められるなんて最高じゃん」
店内は活気に満ち、あちらこちらで笑い声や「おいしい!」の声が飛び交う。その熱気の中で、美晴と天音もまた、心からの安堵と幸福感に包まれていた。
仕事をやり遂げた達成感、そしてご褒美のようなごちそう。そんなひとときが、二人をまた明日への力へとつなげていく。
外の札幌の夜は、さらに深まっていく…
続く
\ファインアロマホップの香り/
6,580円/24缶(送料無料)
\クーポン利用で更に2,000円OFF/
5,980円(送料無料)

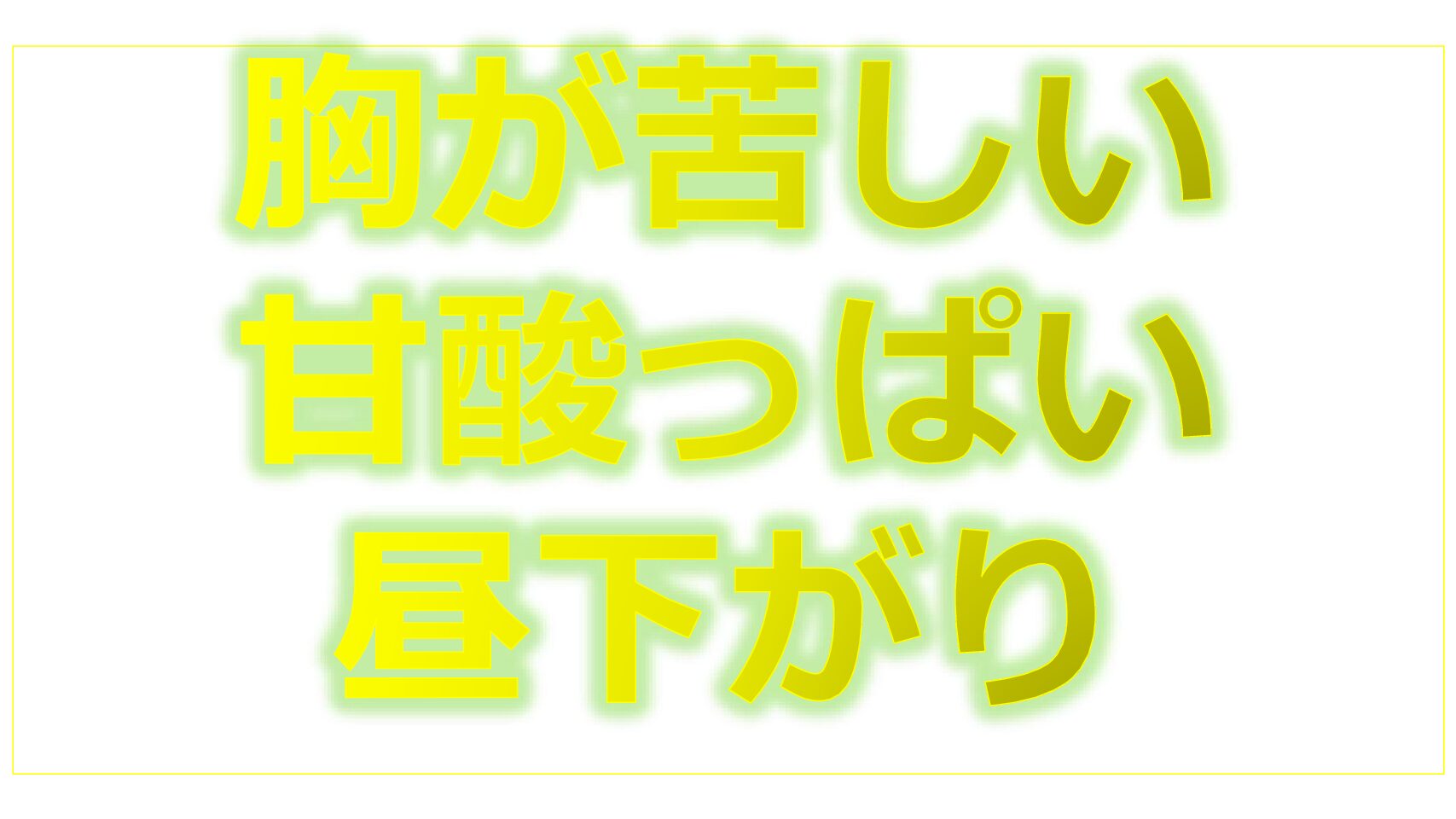

コメント